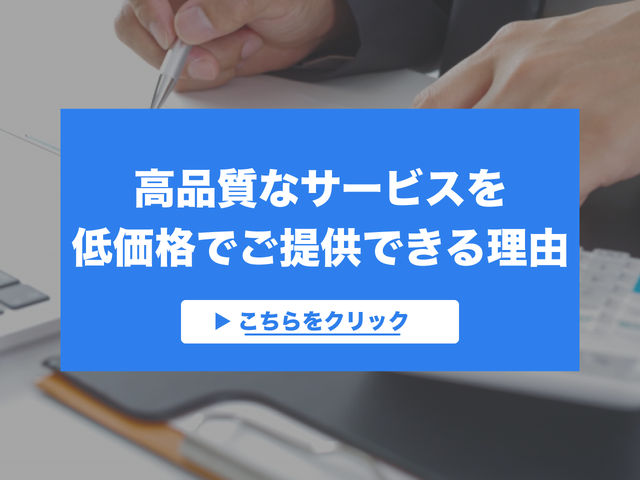堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください
1人社長になる前に知っておきたい!
法人化で節税できる理由と具体的な対策
事業の利益が増えたことで、税負担の重さに頭を悩ませていませんか?
特に個人事業主の方にとって、税金の支払いが事業資金や生活費を圧迫する状況は大きな悩みの一つです。
「もっと手元資金を残す方法はないか」「法人化した方が税負担が軽くなるのか」と考える方も多いのではないでしょうか。
この記事では、節税目的で法人化を検討している個人事業主の方向けに、具体的な節税対策や法人化によるメリットについてわかりやすく解説いたします。
個人事業主よりも法人化した方が節税になる3つの理由
個人事業主の場合、収益が増えるに伴い、所得税の負担が増えていきます。
この負担を軽減する方法として「法人化」が有効です。
法人化には様々なメリットがありますが、特に節税面で大きな効果を期待できます。
以下に、法人化した方が節税になる主な理由を解説します。
- 一定の利益・売上を超えた場合は法人税の税率の方が安くなる
- 経費にできる項目が増え、税負担を軽減できる
- 活用できる節税対策の幅が広がる
1. 一定の利益・売上を超えた場合は法人税の税率の方が安くなる
個人事業主は事業を進める中で利益が大きくなると、所得税の負担も重くなります。
特に年間利益が900万円を超えている場合、法人化した方が税率が安いです。
以下の表でわかるように、年間900万円以上の利益を得ている場合、個人事業主より法人の方が税率が低くなり、節税効果が期待できます。
| 区分 | 課税方式 | 税率 |
|---|---|---|
| 個人事業主(所得税) | 累進課税 | 年間利益900万円以下5%〜23% |
年間利益900万円超 | ||
| 年間利益4,000万円超 最大45% | ||
| 法人(法人税) | 一定税率+軽減税率 (中小企業) | 年間利益800万円以下 約15%〜19% |
| 年間利益800万円超 23.2% |
また、売上が1,000万円を超えている場合、2年後から消費税の納税義務が発生。
消費税の負担は事業規模によって大きな負担となりますが、法人化すれば条件を満たすことで、設立後2年間は消費税の納税が免除される可能性があります。
これにより、法人化した場合、消費税の負担を抑えられるため、資金繰りにも余裕が生まれます。
このように、年間利益が900万円を超え、売上が1,000万円を超えるような事業規模になった場合は、法人化を検討することで節税や資金管理における大きなメリットが得られるでしょう。
2. 経費にできる項目が増え、税負担を軽減できる

個人事業主として事業を行う場合、経費として認められる範囲には一定の制約があります。
一方で、法人化すれば経費の幅が広がり、結果として課税対象となる所得を抑えることが可能。
例えば、個人事業主では自分の「給与」を経費計上できませんが、法人化すると給与を「役員報酬」として受け取れ、経費に含められます。
さらに、法人では「退職金」も経費計上できるため、事業主自身の将来的な資金準備を有利に進められます。
法人化は経費として認められる範囲が広がり、結果として税負担を軽減する効果が期待できるでしょう。
3. 活用できる節税対策の幅が広がる

個人事業主は活用できる節税対策に限りがありますが、法人化すると節税対策の幅も広がります。
特に、事業の規模が大きくなるほど、法人化による節税効果は一層高まります。
前述したとおり、法人化すると「役員報酬」として自分の給与を経費に含められ、課税対象となる所得を減らし、所得税の負担を軽減。
さらに、控除や利益の繰延べなどを活用した節税対策を行いやすいです。
法人化で広がる!1人社長の節税対策5選
法人化して1人社長になると、個人事業主ではできなかった様々な節税対策が可能になります。
ここでは、1人社長だからできる主な5つの節税対策をご紹介。
- 所得を分散して税負担を減らす
- 給与所得控除を活用して所得税を抑える
- 社宅手当を支給して所得税の負担を軽減
- 出張旅費規程を作成して経費計上する
- 法人化で繰越期間が最大9年に延長
1. 所得を分散して税負担を減らす

法人化すると、所得を会社と個人に分散できます。
法人税を支払った後、会社の利益の一部を「役員報酬」という形で自分の給料として受け取ることが可能。
この場合、役員報酬は経費計上できるため、会社の利益が減り、法人税の負担も減ります。
また、役員報酬は所得税の対象となりますが、適切な金額に調整すれば、所得税の負担も軽減。
この仕組みによって、法人税と所得税の負担を分散できるため、結果的に税負担を軽減できます。
2. 給与所得控除を活用して所得税を抑える

個人事業主の場合、売上から経費を引いた利益がそのまま事業主の所得となり、その金額に対して所得税が課税されます。
しかし、法人成りをして役員報酬を受け取るようになると、役員報酬は「給与所得」として扱われ、「給与所得控除」が適用されるため、所得税の計算において控除額を受け取れます。
給与所得控除は、一定金額が控除され、課税対象となる所得額が減少。
法人成りによって、給与所得控除を活用できるため、節税の幅が広がります。
3. 社宅手当を支給して所得税の負担を軽減

個人事業主の場合、自宅の一部を事業に使っていれば、その部分の家賃や光熱費を経費計上できます。
しかし、法人化して自宅を社宅扱いにすれば、会社が家賃や光熱費を負担し、その費用を法人の経費に計上でき、法人税の節税が可能。
加えて、家賃や光熱費を役員報酬に含めるより、別で社宅手当を支給し、その分報酬額を少なくすれば、所得税の負担も軽減できます。
4. 出張旅費規程を作成して経費計上する

社宅手当と同様に、法人が通勤手当や出張手当を支給すると、法人税の節税が可能になります。
個人事業主でも出張費を経費計上できますが、法人化した場合、「出張旅費規程」を作成することで、事前に設定した金額を経費計上できます。
この場合、実際に使った金額が設定金額に満たなくても、規程に基づいて設定された金額を経費として計上可能。
また、通勤手当や出張手当は所得税の課税対象外となるため、所得税の負担も軽減でき、税務面でのメリットが大きくなります。
5. 法人化で繰越期間が最大10年に延長

欠損金とは、企業や事業主が一定期間において、売上や収益よりも多くの支出があった場合に発生する損失のこと。
個人事業主の場合、この欠損金は最大で3年間繰り越して、将来の利益と相殺できます。
しかし、法人化した場合、この繰越期間が最大10年間に延長されるため、長期間にわたって損失を将来の利益と相殺することが可能。
欠損金をより長期間にわたって活用でき、税負担を軽減する大きなメリットが得られます。
紹介した対策以外にも、会社・個人の税負担を減らす方法がいくつかあるので、詳しく節税方法については、以下のリンクをご参照ください。
会社・個人の節税対策について、詳しく知りたい方はこちら
1人社長が知っておくべき節税時の3つのポイント
1人社長として節税対策を実施する場合、いくつか注意点があります。
紹介する注意点を十分考慮して、適切な方法で節税することが大切です。
1. 節税を優先しすぎて事業が疎かになる

節税の目的は税金を減らすためではなく、多くの資金を手元に残すことです。
節税を優先しすぎて事業活動が疎かになると、会社経営が続かなくなってしまいます。
過度な節税は企業の成長を妨げる可能性があるため、無理のない範囲で適切な節税対策を行い、事業の発展とバランスを取ることが重要です。
2. 経費計上のために無駄遣いしない

法人税の負担を減らすために経費を増やそうとする経営者もいますが、無駄な支出が増えると、事業資金が不足し、経営に苦しむ可能性があります。
経費を計上するために無駄なものを購入するのではなく、事業に実際に役立つ備品や設備に投資しましょう。
3. 最新の税制度を確認する

税金に関する法律や制度は定期的に改正されます。
改正により、税率や控除額、課税対象が変更されることがあり、これまで実施していた節税対策が通用しなくなる場合があります。
節税する際は最新情報を確認したり、税理士に相談したりして、適切な対策を取りましょう。
個人事業主から1人社長になるタイミングとは?
ここまで読んで、法人化した方が節税になることはわかったと思いますが、実際にいつ法人化するのが良いのか気になると思います。
個人事業主から1人社長になるタイミングは、年間利益が900万円を超えた場合や、年間売上が1,000万円を超えた場合が一つの目安です。
これらのタイミングで法人化することで、税制面でのメリットが得られます。
詳しく知りたい方は、以下のリンクをご参照ください。
個人事業主が法人化するタイミングとは?
節税だけじゃない!
法人化して1人社長になる2つのメリット
節税目的で法人化する個人事業主の方が多いと思いますが、実は節税以外にも法人化にはいくつかのメリットがあります。
これらのメリットも考慮したうえで法人化を検討しましょう。
- 個人事業主より社会的信用度が上がる
- 融資の審査が有利になる
1. 個人事業主より社会的信用度が上がる

法人は商号や住所、目的代表者、資本金、役員などが登記されるため、個人事業主よりも信用度が高いと言えます。
特に大手企業などは、実績がある個人事業主に対して発注しない場合がありますが、法人化すれば受注できる幅が広がり、より多くのビジネスチャンスを得られる可能性が高くなります。
2. 融資の審査が有利になる

個人事業主の資金調達の方法は、一般的に融資ですが、法人の場合、融資審査が通りやすくなることが多いです。
個人事業主は事業資産と個人資産を分けづらいため、融資審査において個人と事業の区別が難しく、審査が通りにくくなることがあります。
一方、法人化は事業資産が明確に分かれているため、融資を受けやすくなります。
法人化して1人社長になる3つのデメリット
法人化には多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。
税務申告や帳簿管理、決算手続きなどの手間が増え、個人事業主よりも煩雑な事務作業が必要になります。
また、設立費用や維持費用も発生するため、これらの点を事前にしっかりと理解し、検討することが重要です。
- 設立時の費用と赤字の場合の税金負担
- 法人化で発生する社会保険への加入義務
- 自由に使えるお金が制限される
1. 設立時の費用と赤字の場合の税金負担

会社設立には最低でも20万円程度の費用がかかります。
これは、定款の作成や登記申請などの手続きに伴う費用です。
また、個人事業主とは異なり、法人化すると会社が赤字であっても税金を支払わなければならないため、経営状況に関わらずコストが発生します。
会社設立時にかかる費用とは?
2. 法人化で発生する社会保険への加入義務

法人化すると、社会保険への加入が義務付けられます。
社会保険料は会社と本人で折半して負担するため、法人化により社会保険料の負担が発生。
また、従業員が増えると、その分会社の負担額も増加します。
法人化によるメリットは大きいですが、社会保険の負担も念頭においておく必要があります。
3. 自由に使えるお金が制限される

法人化すると、会社資金と個人財産は明確に区別されるため、個人事業主のように自由にお金を使えません。
個人事業主の場合、事業で得たお金は自分のものとして自由に使えますが、法人では会社の運営資金として扱われます。
このため、法人化すると自由に使えるお金が制限され、不便に感じることがあるかもしれません。
1人社長になる際、税理士に依頼した方がいいの?
1人社長になる際、法人化について税理士へ相談や依頼は必須ではありません。
ただ、税理士に会社設立代行を依頼すると、設立にかかる労力や時間を大幅に削減でき、スムーズに進められます。
また、顧問契約を結べば、資金繰りや経営に関するアドバイスを受けられ、経営面での支援が得られます。
会社設立の手続きに時間を取られると、日々の業務に支障をきたす可能性があるため、税理士に依頼すれば本業に集中できるでしょう。
会社設立時に税理士は必要なの?
法人化についてもっと詳しくなりたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください
お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応
0725-53-2251
営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。
和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。
まずはお気軽に
お問合せください
お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)
事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
お問合せについて
営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。
0725-53-2251