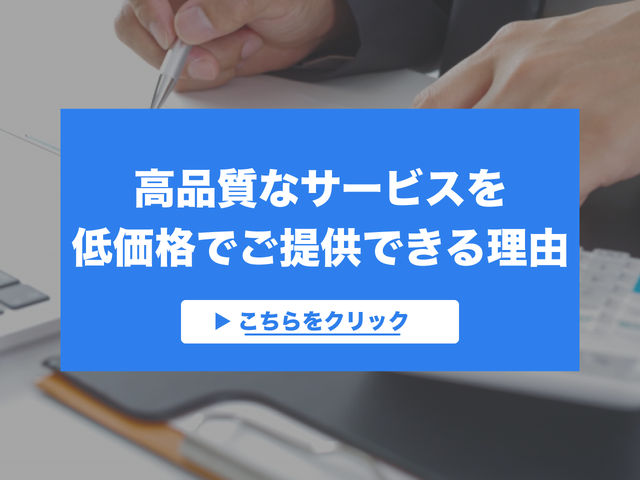堺市・岸和田市・和泉市周辺で税理士をお探しなら、創業40年超の森福会計事務所/森福税理士事務所へご相談ください
社宅を経費にして節税!住宅手当との違いや節税の仕組みを詳しく解説
「社員のために福利厚生を充実させたいけど、社宅が経費になるのか不安」
そんな悩みを抱えた経営者の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、社宅を経費にする方法や社宅が住宅手当より節税になる理由、家賃どこまでは経費計上できるのか、さらに税務上の注意点についても、税理士が分かりやすく解説。
社宅の導入を検討している経営者の方々に、実際に役立つ情報をお届けします。
社宅の方が節税できる!住宅手当との税負担の差
社宅制度を会社に導入しようか悩んでいる方の多くが、住宅手当より節税効果があるのかを気になっていると思います。
結論からお伝えすると、社宅のほうが節税効果が高いです。
では、具体的に社宅と住宅手当はどう違うのか見ていきましょう。
| 項目 | 社宅 | 住宅手当 |
|---|---|---|
| 制度の特徴 | 会社が借りたor購入した住宅を貸与 | 給与に上乗せして家賃補助 |
| 給与課税 | 「賃貸料相当額」を負担すれば非課税 | 所得税・社会保険料の負担増 |
| 会社の経費 | 家賃・減価償却費・借入金利を経費計上可能 | 原則、給与扱いのため経費計上不可 |
| 節税効果 | 高い(会社・従業員双方にメリット) | なし(従業員の手取り減少) |
社宅と住宅手当の大きな違いは、税金の扱いです。
住宅手当は給与とみなされるため、所得税や社会保険料の負担が増えます。
一方、社宅は一定の「賃貸料相当額」を従業員が負担すれば、給与課税されずに住居を貸与できます。
そのため、社宅は住宅手当よりも会社・従業員双方にとって節税メリットが大きい制度と言えます。
借り上げ社宅と社有社宅の違いとは?
社宅導入は企業・従業員にとってメリットが大きいことがわかったところで、ここからは社宅の種類について解説していきます。
社宅は大きく分けて「借り上げ社宅」と「社有社宅」の2種類。
それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく知ることで、自社に合った社宅制度を選べます。
次の内容で詳しく解説していきますので、ぜひご覧ください。
1. 従業員の税負担を軽減「借り上げ社宅」

借り上げ社宅とは、企業が賃貸物件を借りて従業員に提供する社宅制度です。
企業が家賃を支払い、従業員は一部を負担する仕組みになっています。
従業員にとっては、通常の賃貸より安く住めることや、会社負担分が給与課税の対象外となり、所得税や社会保険料の負担が軽減されます。
また、企業にとっても人材確保や福利厚生の充実につながる点が魅力。
一方で、従業員は住む物件の選択肢が限られることがあり、企業側も家賃の設定を誤ると、給与として課税されるリスクがあります。
借り上げ社宅を活用する際は、税務上のルールを正しく理解しておきましょう。
2. スムーズな入居・退去手続きが可能「社有社宅」

社有社宅とは、企業が所有する住宅を従業員に貸し出す制度です。
会社が物件を購入・保有し、従業員は一般の賃貸よりも低い家賃で住めるのが特徴。
社有社宅のメリットは、企業が貸主となり、社員が借主となるため、第三者が間に入らず、スムーズな入居や退去手続きが可能である点です。
一方で、企業には物件の維持管理や固定資産税・修繕費の負担があり、従業員は転職や退職時に退去しなければならないため、住まいの選択肢が限られる場合もあります。
社有社宅は企業と従業員の双方に利点がありますが、長期的なコスト管理や運用の柔軟性が求められる制度です。
社宅を経費に計上するための重要ポイント

まず、従業員から賃貸料相当額の50%以上の家賃を受け取る必要があります。
賃貸料相当額とは、実際の家賃ではなく、国税庁が定めた計算方法で求めた額です。
50%以上の家賃を受け取らない、または金額が50%以下だと、社宅は給与の一部と見なされ、経費として認められなくなります。
経費計上できないと、所得税・社会保険料の課税対象になってしまうので注意が必要です。
社宅の賃貸料相当額を正しく計算する方法
ここからは、賃貸料相当額の計算方法を詳しく解説していきます。
社宅の賃貸相当額は、国税庁が定めたルールに基づいて計算されており、従業員社宅と役員社宅とでは、賃貸料相当額の計算方法が異なります。
従業員社宅の賃貸料相当額の計算方法
従業員社宅の賃貸料相当額は、以下の計算式を基に算出されます。
- [建物の固定資産税の課税標準額]× 0.2%
- 12円 ×[その建物の総床面積(平方メートル) ÷ 3.3(平方メートル)]
- [敷地の固定資産税の課税標準額]× 0.22%
1〜3の合計額の50%以上を家賃として従業員から受け取る必要があります。
この計算式は、借り上げ社宅・社有社宅のどちらにも適用。
具体的な数値を使って、以下の例でわかりやすく説明します。
- 建物の固定資産税の課税標準額:500万円の場合
- 建物の総床面積:100㎡の場合
- 敷地の固定資産税の課税標準額:400万円の場合
| 計算項目 | 金額例 |
|---|---|
| 1. 建物の固定資産税× 0.2% | 500万円 × 0.2% = 10,000円 |
| 2. 12円 × 総床面積÷ 3.3 | 12円 × 100㎡ ÷ 3.3 = 36,364円 |
| 3. 敷地の固定資産税 × 0.22% | 400万円× 0.22% = 8,800円 |
| 合計(1〜3の合計) | 55,164円 |
| 家賃として従業員から受け取る額(50%以上) | 27,582円以上 |
役員社宅の賃貸料相当額の計算方法
役員社宅の場合でも一定の家賃を受け取っていれば給与として課税されません。
ただ、従業員社宅とは違い、建物の規模などによって計算方法が変わります。
建物の規模は大きく分けて以下の2つ。
- 小規模住宅
- 小規模住宅以外
小規模住宅の場合
小規模住宅とは、建物の耐用年数や床面積に基づいて分類されます。
具体的には以下の通りです。
- 耐用年数が30年を超える場合:床面積が99平方メートル以下の住宅
- 耐用年数が30年以下の場合:床面積が132平方メートル以下の住宅
この条件に該当する住宅は、小規模住宅として扱われ、従業員用の社宅と同様の計算式が適用されます。
小規模住宅以外の場合
小規模住宅に該当しない場合、「社有社宅」「借り上げ社宅」「役員社宅」によって賃貸料相当額の計算方法が異なります。
1.社有社宅の場合、以下の2つの合計額の12分の1が賃貸料相当額です。
- 建物の固定資産税の課税標準額 × 12% (耐用年数30年超の建物は10%)
- 敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%
2.借り上げ社宅の場合は、会社が家主に支払う家賃金額の50%、または社有社宅の場合で算出した金額のいずれか高い方が賃貸料相当額となります。
3.豪華住宅に該当する場合、社宅として認められず、一般的な市場価格に基づいた賃貸相当額が適用。
豪華住宅と認定される基準は、床面積が240平方メートルを超える場合や、内外装が高級なもの、プールなどの設備がある場合です。
例えば、役員の個人の趣味や嗜好が反映された住宅は、面積が240平方メートル以下でも豪華住宅と見なされることがあります。
また、役員が借りた住宅を会社が購入・賃借し社宅化する場合がありますが、住宅の規模やデザインに応じて計算方法が異なる点に留意が必要です。
社宅導入前に知っておきたい税務リスクと注意点
社宅を導入する際には、いくつかの税務上のリスクや注意点があります。
社宅導入を検討する際は、これらのリスクを事前に把握し、慎重に取り組むことが大切です。
税理士に相談する際は、社宅の目的や規模、利用方法を具体的に伝え、税務上の取り扱いについてのアドバイスを受けましょう。
無償で提供した社宅は給与扱いになる

無償で社宅を提供すると、その利用分が給与とみなされ、課税所得の一部とみなされます。
具体的には、所得税や住民税が課税されるほか、社会保険料の計算にも影響。
場合によっては、健康保険や厚生年金保険料が増えてしまう可能性もあります。
社会保険料は従業員だけでなく、会社も負担しているため、企業の支払い額も増加。
社宅導入の際は、従業員から受け取る家賃額を確認し、適切に社宅制度を行いましょう。
社内規程なしではトラブルに対応できない

社宅を導入する際、社内規定を策定することが重要です。
社宅に関するルールが明確でないと、従業員から疑問や不満が発生した際、適切に対処できません。
あらかじめ社宅の利用規則や対応方法を盛り込んだ社内規定を整備しておくと、トラブルを未然に防ぎ、スムーズに運営できます。
社内規定を策定すれば、従業員の理解も得やすく、適正な利用が促進されます。
法人名義で運用しないと住宅手当扱いになる

借り上げ社宅を利用する場合、賃貸借契約は法人名義でなければなりません。
従業員が自分で選んだ物件を借り上げ社宅にする制度でも、契約は法人名義で行う必要があります。
もし従業員に賃貸借契約を締結させ、その家賃に対する補助を行う場合、これは住宅手当に該当。
そのため、住宅手当として補助を行うのか、社宅を用意するのか、事前に方針を決定し、適切な対応をとりましょう。
光熱費や駐車場代は従業員が負担する

社宅の光熱費や駐車場代は、従業員が負担することになります。
企業が従業員の光熱費や駐車場代を負担した場合、その金額が給与として扱われるため、従業員に対して所得税や住民税が課税されます。
企業側も、従業員の負担を減らすための方法として、税務面をしっかりと考慮した制度設計が重要です。
社宅の更新料に消費税はかかるの?

社宅を提供する企業の立場として、社宅の更新料に関する消費税の取り扱いについて気になる方も多いかと思います。
特に、経理や税務の面で適切に処理したいと考えている経営者の方には重要なポイント。
社宅の更新料は、契約更新時に発生する費用のこと。
企業が社宅を貸し出す場合、家賃の負担だけでなく、入居一時金や更新料も全額負担することが多いです。
社宅の更新料に関しては、消費税は課税されません。
ただ、仲介手数料や鍵の交換費用、管理会社による物件整備費用などは消費税が課税される対象となるので注意しましょう。
社宅導入は節税以外にも2つのメリットがある
ここからは、社宅の節税以外のメリットを解説していきます。
社宅は税制面でのメリットに加え、従業員の福利厚生を充実させ、仕事と生活のバランスをサポートする重要な制度です。
1. 新入社員の定着率を高める

企業が提供する福利厚生の充実は、就職・転職活動をしている人にとって大きな魅力です。
福利厚生が充実している企業では、働きやすい環境が整っていると言えるため、新入社員の定着率向上にもつながります。
企業にとっても、競合他社より先に優秀な人材を確保できるきっかけになり、求職者と企業の双方にとって良い結果を生み出します。
2. 従業員の業務効率や満足度が向上

遠いところから通勤している従業員がいる場合、社宅を導入することで、通勤時間が短くなり、通勤のストレスを軽減できます。
通勤時間の短縮により、仕事に集中できる環境が整い、業務効率も向上する可能性も。
このように、従業員の満足度が向上し、企業全体の生産性も高まるでしょう。
社宅導入で避けられない手続きの手間とは?

社宅制度は企業と従業員双方にメリットがありますが、デメリットも存在します。
すべての企業や従業員に適しているわけではなく、導入時には慎重な検討が必要です。
社宅は賃貸契約を法人名義で行う必要があり、その手続きに手間がかかります。
具体的には、各種事務手続きや設備故障、近隣トラブルへの対応も求められます。
また、空室が多ければ、家賃収入が減少し、企業がその負担を負うことに。
自社管理の社有社宅では、大規模な修繕時に大きな費用と手間がかかることも考慮するべきポイント。
社宅制度を導入する際には、これらのデメリットも含めて慎重に判断しましょう。
社宅活用と併せてできる節税対策

社宅の節税と併せてできる節税対策には、いくつかの方法があります。
これらの方法をうまく組み合わせることで、税負担を効果的に軽減することが可能です。
まず、役員報酬の見直しが効果的です。
役員報酬額を適切に設定することで、所得税や法人税の負担を抑えられます。
次に、出張手当の支給も節税の手段。
交通費や宿泊費、食事代などが対象となり、これらを経費計上することで課税対象額を減らせます。
これらの対策を実施する際には、税理士に相談することも一つの方法。
税務署からの指摘を避けるためにも、専門家の意見を取り入れることが重要です。
さらに詳細な節税対策については、以下の記事を参考にしてください。
社宅と併せてできる節税対策について詳しく見る
社宅の節税のご相談は森福税理士事務所へ
本記事では、社宅導入を検討している経営者向けに、住宅手当との比較、社宅を経費にする方法を中心に紹介してきました。
社宅の導入によって税金面でのメリットが得られることは理解できたかと思いますが、実際に導入するにあたって不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
社宅の導入を検討しているものの、具体的な方法や税務面でのリスクについて不安がある方は、ぜひ税理士に相談してみてください。
この記事を書いた森福税理士事務所では、経営者一人ひとりの状況やニーズに合わせたアドバイスを行い、社宅導入をはじめとする様々な節税対策についてもしっかりサポートいたします。
大阪の和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
安心して最適な節税対策を進められるようお手伝いさせていただきます。
税金をもっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください
お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応
0725-53-2251
営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。
和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。
まずはお気軽に
お問合せください
お問合せはこちら

営業時間(9:00~17:00)
事前にご予約があれば、時間外のご相談も承ります。
休業日
土曜日・日曜日・祝日
お問合せについて
営業時間外でもお電話でのご対応は可能です。お電話が繋がらない場合は、少し時間をあけてもう一度お電話いただければ幸いです。
また、お問合せフォームからお問合せいただければ、当事務所よりご連絡いたします。
0725-53-2251