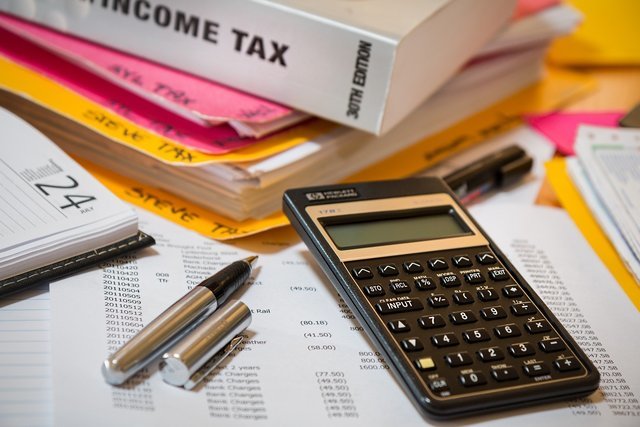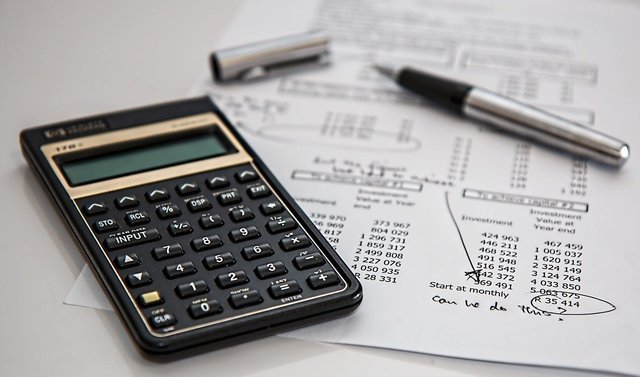初めてでもわかる「連結決算」ガイド

グループ企業になると、各会社の決算だけでなく、連結決算を行う必要があります。
通常の決算と連結決算がどのように違うのか、税理士がわかりやすく解説していきます。
グループ全体の経営成績を明確にする「連結決算」
子会社が存在するグループ企業全体の経営成績とキャッシュフローの状況を把握するために行う、連結決算。
グループ企業内のやり取りを排除した、連結財務諸表が作成されるため、グループ企業全体の正確な事業結果が分かります。
連結決算が必要となる2つの条件
下記2つの基準を満たす企業は、連結決算を行う必要があります。
- 有価証券報告書を提出している
- 大会社である
投資家が公正な判断をするために必要な「有価証券報告書」
上場企業が開示する情報である有価証券報告書。
投資家が株の購入を検討している会社の財務状況を確認するための書類で、投資家が正確に株を購入する企業の状況を把握するためにも、連結決算が必要となります。
大会社の定義とは
下記いずれかの条件を満たす企業は「大会社」とみなされます。
- 資本金5億円以上
- 負債総額200億円以上の株式会社
連結対象となる子会社の条件
グループ企業の中には、多くの子会社が存在し、全ての子会社を連結決算の対象とするのは困難な場合もあります。
そのため、連結決算の対象となる子会社は、下記1〜3の条件を満たす場合とされています。
| 条件 | 保護する議決権 | 子会社判断基準 |
|---|---|---|
条件1 | 過半数 | |
| 条件2 | 40%〜50% | ・緊密者 ・同意者が定めらた数以上いる ・役員関係等一定の条件を満たす |
| 条件3 | 0%〜40% | ・緊密者 ・同意者が過半数以上いる ・役員関係等一定の条件を満たす |
投資家の不利益を生まないように必要な連結決算

グループ企業内で、投資家や債権者に不利益な操作が起こらないように、条件を満たすグループ企業には「連結決算」が求められています。
例えば、別の子会社から特定の子会社にお金を集めることで、「経営成績を良く見せて投資家からお金を集める」といったことができないようになっています。
決算する企業側が得られる連結決算のメリット
企業側が得られる連結決算のメリットは、下記2点です。
- グループ企業全体の経営状況を正確かつ網羅的に把握できる
- 銀行から融資を受ける期間が短縮できる可能性が高い
銀行が融資を検討する際、子会社や関連会社間での取引状況を調査します。
連結決算を行なっていると、取引状況が明確になっているため、融資審査がスムーズに進み、融資までの期間が短縮できます。
連結決算のデメリット

連結決算を行うこと自体で発生するデメリットはありませんが、連結決算の処理に時間も手間もかかります。
各子会社の決算資料を合算したり、修正する作業はかなり大変です。
勘定科目が違っていたり、会計システムの利用の有無など、会社ごとの経理の違いが多いほど、担当者の負担を増えます。
それだけでなく、会計監査役・会計監査人の監査を受ける必要もあります。
4つの資料からなる「連結財務諸表」
通常の決算と同じく、連結決算では財務諸表を作成します。
連結決算で作成する財務諸表は「連結財務諸表」といい、下記4つの資料で構成されます。
- 連結貸借対照表
- 連結損益計算書
- 連結キャッシュフロー計算書
- 連結株主資本等変動計算書
1. グループ全体の財務状況を表す「連結貸借対照表」
親会社・子会社の資産・負債等を合算した上で、グループ企業内の資本金や投資金などのやり取りを相殺消去して作成します。
連結貸借対照表の作成には、下記2つの方法があります。
- 全部連結=親会社の支配力が認められる子会社に用いられる方法
- 持分法=親会社の影響力が認められる関連会社
2. グループ全体の経営成績を表す「連結損益計算書」
親会社と子会社の収益費用を合算した、グループ企業全体の損益計算書が「連結損益計算書」です。
「連結損益計算書」からは、グループ企業内での売上や仕入れなどの取引は相殺・未実現損益の消去が行われます。
3. 会計期間における収支を表す「連結キャッシュフロー計算書」
「連結キャッシュフロー計算書」の作成は、一般的に連結貸借対照表と連結損益計算書から作成する、簡便法が用いられます。
ただ、原則としては、各会社のキャッシュフローから計算する方法となっています。
4. 純資産の変動を報告する「連結株主資本等変動計算書」
純資産が変動した事由を明らかにするために作成する「連結株主資本等変動計算書」。
連結貸借対照表に記載された純資産項目の下記項目を記載することで、1年間に何の資産がどのような理由で変動したかが分かります。
- 前期末残高
- 当期変動額
- 変動事由
- 当期末残高
連結財務諸表作成までの4つの流れ
会社ごとに個別の財務諸表を作成
まずは各会社の決算手続きを進め、個別に財務諸表を作成していきます。
注意点としては、会計上の処理方法を統一させておくことです。
会計上の処理方法を統一しておかないと、連結決算する際に整合性が取れなくなります。
個別財務諸表の合算
各会社の財務諸表の作成が終わったら、それらを合算していきます。
連結修正仕訳の実行
合算した内容から、グループ企業内のやり取りを除くために、下記の修正を行なっていきます。
- 親子間取引の相殺
- 未実現損益の消去
連結財務諸表の作成
連結修正を加えた、連結財務諸表を作成します。
まとめ
連結決算そのもの、連結決算を行わなければいけないグループ企業の条件、連結決算の流れなどを解説してきました。
通常の決算と合わせて行う必要があり、子会社の数が多ければ多くなるほど、処理が大変になっていきます。
ただ、事前の準備の仕方によっては、その負担を減らせます。
決算時期に慌てることがないよう、税理士に相談しながら、連結決算の準備を進めていきましょう。
税務会計にもっと詳しく知りたい方は
こちらのページも合わせてご覧ください
お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応
0725-53-2251
営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。
和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。