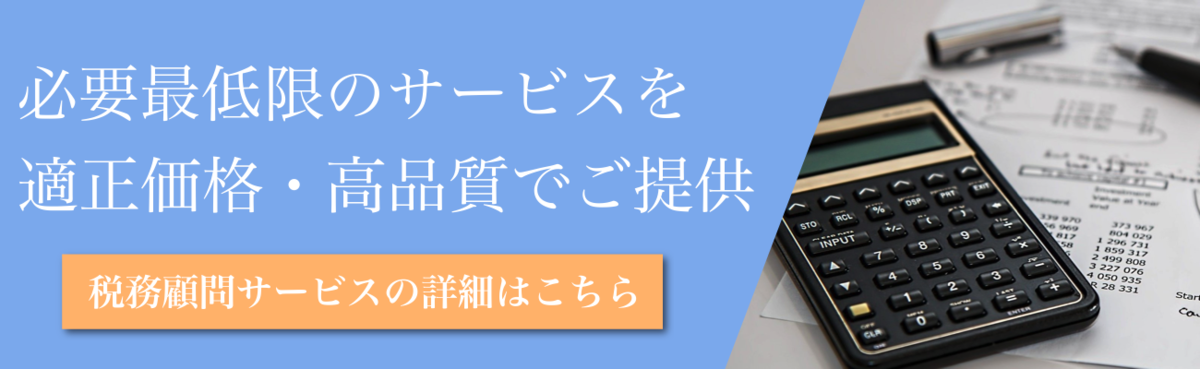節税
給与からの控除額の誤り

給与からの控除額については、健康保険や厚生年金の社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税などがあげられます。
社会保険料は、年に何回か改定されます。
おおむね3月、9月です。
住民税は、6月から翌年の5月分までが、5月ごろに金額が送付されてきます。
大阪府高石市のお客様が、今年の6月以降の住民税を、今までと同じ(=5月までの住民税)を引いていたので、どうするべきかということでした。
対象の従業員様が在籍している場合
ご相談いただいた会社様の場合、まだその従業員様が在職されていましたので、次月で、今年の6月からの正しい住民税額と、すでに差し引いてしまった、まちがった昨年同様の住民税額との差額を計算して、次月に修正します。
住民税は、年額を12ケ月で均等に割り、毎月が同じ金額になります。ただし12ケ月で均等に割り切れない時は、端数が初めの6月に入り、調整されます。
そのため6月だけが少し多くなり、7月~翌年の5月までが毎月同じ金額となります。
ここで例えば7月の給与計算の際に、6月で差し引いた住民税の金額と同じ金額を差し引いてしまった場合は、8月の給与計算の際に、7月で多く差し引いてしまった分の金額を追加で支給する形にします。逆に差し引いてしまった金額が少ない場合は、次月の給与から追加で徴収する形にすれば、問題はありません。
ただしこのいずれの場合も、市町村から届いている住民税の納付書は、記載通りに納付されて下さい。
対象の従業員様が在籍していない場合
ただ、上記のような場合、もしすでにその従業員様が、退職されていた場合は複雑になります。
7月の給料の支給額を住民税を間違って手取り額を支払った場合、
すでに差し引いてしまった金額が多い場合は、追加で支給する形ですので、追加分を何らかの形で支給すればよいのですが。
差し引いてしまった金額が少ない場合は、次月の給与から追加で徴収する形ができません。
退職により、次月に支給するべき給料がない状況です。
この場合は、本人にその旨を伝えて、徴収するということになります。
社会保険料・雇用保険料等の天引きミスも同じ処理で対応
住民税以外の、給与から控除する健康保険や厚生年金の社会保険料、雇用保険料、源泉所得税なども住民税と同じ対応方法で税務上・会計上は問題ありません。
税務上・会計上の処理を適切に行うことも大切ですが、天引きミスが発生した従業員には事情を説明し、謝罪することも同じぐらい大切です。
また、従業員からの信用を失わないように、天引きミスが発生しないような仕組みを作りましょう。
森福税理士事務所の税務顧問サービスでは、給与計算もご提供可能です。
天引きミスが発生してしまった方は、この機会にプロへ依頼することもご検討してみてはいかがでしょうか。
お問合せはこちら

堺市・岸和田市・和泉市を中心に全国対応
0725-53-2251
営業時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※「ホームページを見ました」とお電話下さい。
和泉市・堺市・岸和田市を中心に全国対応しております。お気軽にご相談ください。